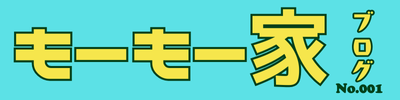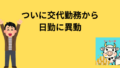春から新一年生。
「うちの子、本当に一人で通学できるの?」
小学校入学を控えると、多くの保護者がこの不安に直面しますよね。
特に通学路の危険や防犯面は見逃せません。
この記事では、小学1年生の安全な通学を実現するための具体的な対策や便利な見守りアイテム、家庭でできる教え方をわかりやすく紹介します。
通学初日を安心して迎えるために、今できる備えを一緒に確認していきましょう。
「いざ入学!」の前にしておくべき“本番シミュレーション”

小学校入学と同時に始まる「一人での通学」。
親にとって最も心配なのは、「ちゃんと安全に学校まで行けるのか?」という点ではないでしょうか。
その不安を解消する第一歩が、「登下校シミュレーション」です。
実際の通学時間に、ランドセルを背負わせて、親子で本番さながらに歩いてみることで、思わぬリスクや子どものクセを発見できます。
シミュレーションのポイント:親がチェックすべき4つの視点
① 子どもの「動線」と視線を観察
・フラフラ歩いていないか
・スマホや景色に気を取られていないか
・横断歩道で止まって左右確認しているか
② 危険な箇所の“気づき”
子どもは「車が来るかもしれない場所」「死角になる場所」に気づきません。
以下のような場所は要注意です。
・信号のない横断歩道
・公園の脇や駐車場の出入り口
・見通しの悪いT字路
親が気づいた危険ポイントは、子どもと一緒に立ち止まって、「ここはこうしようね」と確認しましょう。
③ 時間を計測する
毎朝の準備や帰宅時間を想定し、実際に歩く所要時間を測っておくと、生活リズムにも組み込みやすくなります。
④不審者への対応
知らない人に声をかけられたときの対処法(大声で断る、逃げる、助けを求める)を教えます。
よくある子どもの「危ないクセ」とその対処法
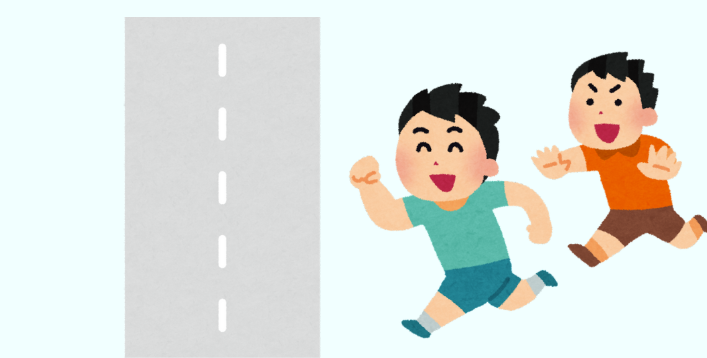
通学シミュレーションをしていると、多くの親が以下のような“ヒヤリ”に出会います。
・横断歩道の直前で走り出す
→必ず一緒に「立ち止まって、右左!」と声かけして習慣化
・友だちとおしゃべりして注意散漫
→少し距離を空けて歩かせて観察。「○○ちゃんと一緒のときも気をつけてね」と声がけ
・信号が変わりそうでも渡ろうとする
→「黄色は止まるサイン」と繰り返し教える。親も実演を意識
練習は「回数より質」が大事
1回の練習で完璧にできる子どもはいません。
でも、回数をこなすだけではなく、「何をどう気をつけるか」を一緒に確認しながら歩くことで、子どもは確実に安全意識を育てていきます。
最初は毎回付き添って、慣れてきたら少しずつ距離を取る…というように、“見守りの段階的なステップ”を意識すると、親の不安も和らぎますよ。
見守りアイテムの活用と地域との連携
子どもの安全を守るために、見守りグッズの活用や地域との連携も重要です。
防犯ブザーの取り付け
防犯ブザーをランドセルの取り出しやすい場所に付け、使い方を練習させます。
GPS端末の活用
子どもの位置情報を確認できるGPS端末を持たせ、登下校の状況を把握します。
地域の見守り活動
近隣の方々と挨拶を交わし、地域全体で子どもを見守る体制を築きましょう。
避難場所の確認
「子ども110番の家」やコンビニなど、緊急時に駆け込める場所を把握しておきましょう。
学校や地域の情報収集
学校からの連絡や地域の防犯情報をチェックし、最新の情報を把握しておきます
あとがき
小学校生活のスタートは、親にとっても子どもにとっても大きな一歩。
不安を減らすためには、事前の準備と繰り返しの声かけが何より大切です。
今回ご紹介した安全対策を取り入れながら、お子さんが安心して登下校できる環境を整えてあげてください。
毎日の通学が、成長の一歩になることを願っています。